6月。雨が続き、空はどんより、傘が手放せないこの季節。日本列島に梅雨前線が張りつくこの時期、多くの人が「なんとなく気分が晴れない」「朝からだるい」「仕事に身が入らない」といった不調を訴えることがあります。それ、もしかすると「梅雨うつ(季節性の気分変化)」かもしれません。今回は、この6月特有の「心の不調」の原因と、今日からすぐできる対策をご紹介します。
梅雨うつってなに?──気づきにくい心の変化

出典:photo-ac.com
「梅雨うつ」とは、正式な医学用語ではありませんが、季節の変化、特に梅雨時の気候条件によって心身に不調が現れることを指します。これは「季節性情動障害(SAD)」の一種と捉えることもでき秋や冬に限らず、6月にも多くの人が体験する現象です。
主な症状
• 朝起きられない、眠気が取れない
• 食欲がない、または食べすぎる
• やる気が出ない、興味関心が薄れる
• 頭痛や肩こり、だるさが続く
• 不安感、イライラ、涙もろさ
これらの症状が1週間以上続く場合、体の疲れではなく心のSOSかもしれません。
なぜ6月に不調が出やすいのか?
① 日照時間の減少
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
梅雨になると曇りや雨の日が続き、日照時間が極端に減少します。太陽光を浴びる時間が短くなると、「セロトニン」という幸福ホルモンの分泌が減少。これにより気分が落ち込みやすくなります。
② 気圧の変化
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
低気圧が長期間続くことで、自律神経のバランスが乱れます。交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなると、疲れやすさや頭痛、だるさなどの不調を感じるようになります。
③ 湿気と寒暖差
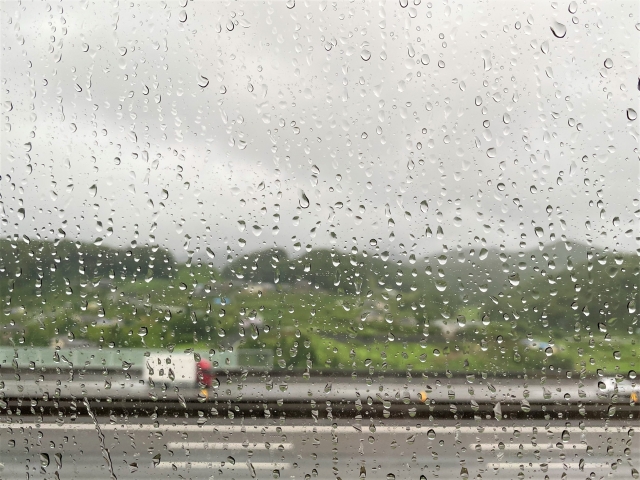 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
ジメジメとした湿気や1日の寒暖差も、体にストレスを与えます。これらの気象条件が重なることで、体のリズムが崩れ、心にも影響を及ぼすのです。
梅雨うつの対策5選!今日からできるケア方法
① 朝の光を意識的に浴びる
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
曇っていても窓際に立つだけでもOK。朝に自然光を浴びることで、体内時計が整い、セロトニンの分泌が促進されます。雨の日でもカーテンを開け、できれば15分は外の光を浴びてみましょう。
② 運動で気分転換を
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
軽いストレッチやウォーキング、室内ヨガなど、日常に「動き」を取り入れることが重要です。運動はセロトニンの分泌を助け、血行促進にもつながります。
③ 湿度対策をする
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
湿度が高いとカビやダニも発生しやすく、身体にも悪影響。除湿機やエアコンのドライ機能、除湿剤を活用し、室内環境を快適に保ちましょう。
④ 食事でセロトニンをサポート
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
セロトニンの材料となるトリプトファンを多く含む食品(バナナ、納豆、豆腐、チーズなど)を意識して摂りましょう。ビタミンB6やマグネシウムも一緒に摂ると効果的です。
⑤ 無理をしない、休む勇気を持つ
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
調子が出ないときは、「がんばらなきゃ」と自分を責めるよりも、思い切って休息をとることも大切です。心と体を守ることが、長期的には効率を上げることにもつながります。
自分だけじゃない。みんな6月はしんどい
SNS上では、「6月になると毎年しんどくなる」「何もしてないのに疲れる」といった声が多く見られます。つまり、あなたが感じている不調は特別なことではありません。「なんだかしんどい」と感じるのは、気候や環境による自然な反応でもあります。無理にポジティブになろうとせず、「そういう季節だから仕方ないよね」と自分をゆるめることが、結果的に心の負担を軽くしてくれます。
6月だからこそ、自分にやさしく
 出典:photo-ac.com
出典:photo-ac.com
じめじめとした空気に包まれた6月は、無意識に体も心も疲れがち。だからこそ、自分の気分の変化に耳を傾けてあげてください。晴れ間が差す日には、少し散歩してみる。朝起きたらカーテンを開けて深呼吸してみる。しんどいときは無理せず、「今日はゆっくりしよう」と思える余裕を持つ。季節と上手につきあって、自分の心と体をメンテナンスする6月にしてみませんか?
おわりに
「梅雨うつ」という言葉に、初めて触れた人も多いかもしれません。でも、実は誰にでも起こりうる、身近な現象です。だからこそ、「気のせい」や「甘え」で片付けず、心の健康にも目を向けることが大切です。雨の日が続く6月だからこそ、自分の気持ちに敏感になり、心を守る行動を一つずつ積み重ねていきましょう。
